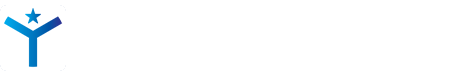建設業許可の中でも需要の高い「とび・土工・コンクリート工事」。許可取得には専任技術者の要件を満たす必要があり、実務経験証明は重要なポイントです。本記事では、とび・土工工事の内容、専任技術者の要件、そして実務経験証明の事例を詳しく解説します。
とび・土工・コンクリート工事とは?許可取得の基本

工事の種類と具体例
とび・土工・コンクリート工事は、建設工事の中でも非常に基礎的な役割を担っています。これらの工事は、建物を建てる上で必要となる地盤の整備や、構造物を支えるための基礎工事など、建物の安全性や耐久性を左右する重要な工程を担います。
具体的には、足場の組立、解体、重量物の運搬、土砂の掘削、盛土、締固め、コンクリートの打設、型枠の設置、鉄筋の配置など、多岐にわたる作業が含まれます。これらの作業は、専門的な知識と技術を要するものであり、安全管理も徹底する必要があります。
具体的な工事例としては、高層ビルやマンションなどの建設現場における足場組立、道路やトンネルの建設における掘削や盛土、橋梁の建設におけるコンクリート構造物の築造などが挙げられます。〇〇建設様のビルの足場組立や、△△工業団地の造成工事などは、まさにこれらの工事の典型的な例と言えるでしょう。これらの工事は、私たちの生活基盤を支える上で欠かせないものであり、建設業の中でも特に重要な位置を占めています。安全かつ確実に工事を進めるためには、熟練した技術者と適切な施工計画が不可欠です。
許可が必要なケース
建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う場合には、建設業許可が必要となります。
具体的には、工事1件の請負代金の額が500万円以上となる場合、または建築一式工事において、工事の請負代金の額が1,500万円以上、もしくは延べ面積が150㎡以上となる場合に許可が必要となります。とび・土工・コンクリート工事も例外ではありません。 この許可制度は、建設工事の適正な施工を確保し、建設業者の資質の向上を図ることを目的としています。無許可で営業すると、建設業法違反となり、罰則の対象となるため注意が必要です。
具体的には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、無許可営業を行った場合は、公共工事の入札に参加することができなくなるなどのデメリットもあります。建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たす必要があり、その手続きも煩雑であるため、専門家への相談も検討すると良いでしょう。 特に、とび・土工・コンクリート工事は、専門性が高く、安全管理が重要な工事であるため、許可取得の際には、技術者の資格や実務経験などが厳しく審査されます。許可を取得せずに工事を請け負うことは、発注者からの信頼を損なうだけでなく、法律違反となるため、必ず許可を取得するようにしましょう。
解体工事業との違い
解体工事も建設業許可が必要な工事ですが、とび・土工工事とは異なる業種に該当します。
建設業許可は、建設工事の種類ごとに区分されており、それぞれ許可要件が異なります。 解体工事業は、建築物や構築物などを解体する工事を指します。一方、とび・土工工事は、足場の組立、掘削、コンクリート打設など、建設工事の基礎的な部分を担う工事です。両方の工事を行う場合は、それぞれの許可が必要となります。
例えば、建物を解体し、その跡地に新たな建物を建設する場合、解体工事業の許可と、とび・土工・コンクリート工事の許可の両方が必要となることがあります。解体工事は、近年、環境問題への関心の高まりとともに、その重要性が増しています。解体工事においては、アスベストなどの有害物質の適切な処理や、騒音・振動の抑制などが求められます。
また、解体後の廃棄物のリサイクルも重要な課題となっています。解体工事を行う際には、これらの点に注意し、適切な施工を行う必要があります。解体工事業の許可を取得するためには、解体工事に関する専門的な知識や技術が必要となります。許可取得の際には、解体工事に関する実務経験や、解体工事施工技士などの資格が重視されます。解体工事を行う際には、必ず解体工事業の許可を取得し、適切な施工を行うようにしましょう。
専任技術者の要件:実務経験が重要

専任技術者の資格要件
建設業許可を得るためには、営業所ごとに専任の技術者を配置する必要があります。この専任技術者は、その営業所において、建設工事に関する技術的な事項を統括し、適正な施工を確保する役割を担います。
とび・土工・コンクリート工事の場合、一定の資格を持つ者、または指定学科卒業後一定の実務経験を持つ者、あるいは10年以上の実務経験を持つ者が専任技術者となることができます。 具体的には、1級または2級の土木施工管理技士、1級または2級の建築施工管理技士、技術士(建設部門、総合技術監理部門)、建築士などの資格を持つ者は、専任技術者となることができます。また、土木工学や建築学などの指定学科を卒業し、3年または5年の実務経験を持つ者も、専任技術者となることができます。 さらに、これらの資格や学歴を持たない場合でも、10年以上のとび・土工・コンクリート工事に関する実務経験を持つ者は、専任技術者となることができます。
専任技術者は、建設業許可を取得する上で非常に重要な要件であり、その選任には慎重を期する必要があります。専任技術者の資格要件を満たしているかどうかは、建設業許可申請の際に厳しく審査されます。専任技術者の要件を満たしていない場合、建設業許可を取得することができません。そのため、専任技術者の選任にあたっては、事前に資格や実務経験を十分に確認しておくことが重要です。
指定学科と実務経験の組み合わせ
土木工学や建築学などの指定学科を卒業した場合、一定期間の実務経験を経ることで専任技術者になることができます。
ここでいう指定学科とは、建設業法施行規則で定められた学科であり、土木工学科、建築学科、都市工学科などが該当します。これらの学科を卒業した場合、学歴に応じて必要な実務経験年数が異なります。 例えば、大学卒業の場合、3年以上の実務経験が必要となります。高等専門学校卒業の場合は、5年以上の実務経験が必要です。専門学校卒業の場合は、学校の種類や学科によって必要な実務経験年数が異なります。実務経験とは、実際に建設工事の施工に携わった経験を指します。具体的には、工事の計画、設計、施工管理などの業務に従事した経験が該当します。実務経験を証明するためには、工事の契約書、注文書、請求書などの書類が必要となります。これらの書類を通じて、実際に工事に携わったことを証明します。
また、経験を証明する企業の建設業許可通知書の写しなども有効です。実務経験の年数は、最終学歴によって異なり、大学卒業の場合は3年以上、高等専門学校卒業の場合は5年以上、高校卒業の場合は10年以上の実務経験が必要となります。これらの要件を満たすことで、専任技術者として認められ、建設業許可を取得することができます。実務経験は、単に工事現場で作業をしただけでなく、技術的な知識や経験を伴うものでなければなりません。
実務経験証明のポイント
実務経験を証明するためには、客観的な証拠となる書類を準備する必要があります。
最も重要な書類は、工事の契約書、注文書、請求書などです。これらの書類には、工事の名称、場所、期間、金額などが記載されており、実際に工事に携わったことを証明する上で非常に有効です。 これらの書類に加えて、工事写真や工事日報なども実務経験を証明する上で役立ちます。工事写真は、工事の進捗状況や完成状況を示すものであり、実際に工事に携わったことを視覚的に証明することができます。工事日報は、その日にどのような作業を行ったかを記録したものであり、実務経験の内容を具体的に示すことができます。
また、経験を証明する企業の建設業許可通知書の写しなども有効です。これは、その企業が建設業許可を受けており、適法に建設工事を行っていることを証明するものです。実務経験を証明する際には、これらの書類をできるだけ多く収集し、信憑性を高めることが重要です。
また、これらの書類は、原本または原本証明されたものでなければなりません。 コピーの場合は、原本と相違ない旨の証明が必要となります。実務経験を証明する書類は、建設業許可申請の際に提出する必要があります。これらの書類に基づいて、審査機関が実務経験の有無や内容を審査します。実務経験が不足していると判断された場合、建設業許可を取得することができません。そのため、実務経験を証明する際には、十分に準備を行い、必要な書類を漏れなく提出することが重要です。もし、実務経験の証明に不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
実務経験証明の事例:許可取得のヒント

ケース1:10年の実務経験で許可取得
Aさんは、建設業許可を持たない企業で10年間、とび・土工工事の実務経験を積みました。許可取得のため、過去の工事に関する資料集めに奔走しました。まず、過去に携わった工事の契約書や請求書などを可能な限り収集し、実務経験を証明するための準備を進めました。しかし、10年前の書類となると、紛失していたり、保管状況が悪く判読が難しかったりと、苦労の連続でした。 そこでAさんは、過去の取引先や関係者に連絡を取り、当時の状況を証言してもらうことにしました。〇〇建設株式会社の上田様は、Aさんの長年の仕事ぶりを知っており、推薦状を快く引き受けてくださいました。上田様からの推薦状には、Aさんの技術力や誠実さ、そして現場での実績などが具体的に記載されており、実務経験を証明する上で大きな力となりました。
また、Aさんは、自身が作成した工事の計画書や図面なども収集し、実務経験の内容を具体的に示すことに努めました。 これらの資料を総合的に判断した結果、Aさんの実務経験は十分に認められ、無事に建設業許可を取得することができました。
この事例からわかるように、10年の実務経験は、建設業許可取得のための強力な武器となります。しかし、実務経験を証明するためには、客観的な証拠となる書類や関係者の証言が不可欠です。そのため、日頃から工事に関する資料を整理・保管し、関係者との良好な関係を築いておくことが重要です。また、実務経験の内容を具体的に示すことができる資料を準備することも大切です。
ケース2:資格取得後に実務経験を積んで許可取得
Bさんは、土木施工管理技士の資格を取得後、3年間とび・土工工事の実務経験を積みました。Bさんは、資格取得前から建設業界に興味があり、独学で土木に関する知識を学んでいました。そして、資格取得を機に、本格的に建設業界で働くことを決意しました。 資格取得後、Bさんは、とび・土工工事を専門とする建設会社に入社し、現場での実務経験を積むことにしました。入社当初は、現場での作業に戸惑うこともありましたが、先輩社員の指導や自身の努力によって、徐々にスキルアップしていきました。Bさんは、現場での作業だけでなく、工事の計画や設計、施工管理など、幅広い業務に携わることで、実務経験を積んでいきました。また、Bさんは、資格取得後も継続的に学習を続け、土木に関する知識を深めることに努めました。 その結果、Bさんは、3年間の実務経験を通じて、とび・土工工事に関する深い知識と高い技術を身につけることができました。そして、Bさんは、資格と実務経験を組み合わせることで、比較的スムーズに建設業許可を取得することができました。
この事例からわかるように、資格取得後に実務経験を積むことは、建設業許可取得のための有効な手段となります。資格は、知識や技術を証明するものであり、実務経験は、現場での実践的な能力を証明するものです。資格と実務経験を組み合わせることで、建設業許可取得の可能性を高めることができます。また、資格取得後も継続的に学習を続けることで、知識や技術を維持・向上させることが重要です。
ケース3:経験豊富な取締役を招聘して許可取得
D社は、新たに建設業に参入するため、とび・土工工事の経験が豊富なCさんを取締役として招聘しました。D社は、以前から建設業への参入を検討していましたが、専門的な知識や経験を持つ人材が不足しており、なかなか踏み切ることができませんでした。そこで、D社の経営陣は、建設業界で長年の経験を持つCさんに白羽の矢を立て、取締役として招聘することを決意しました。 Cさんは、30年以上にわたり、とび・土工工事の現場で経験を積んできたベテランであり、その知識と経験は非常に豊富でした。Cさんの加入により、D社は、建設業に関する専門的な知識や経験を大幅に強化することができました。Cさんは、取締役として、建設業に関する戦略の策定や、現場での技術指導などを担当し、D社の建設業参入を全面的にサポートしました。また、Cさんの実務経験と役員としての経験を合わせて、建設業許可を取得するための要件を満たすことができました。D社は、Cさんの貢献により、無事に建設業許可を取得し、建設業界への参入を果たすことができました。
この事例からわかるように、経験豊富な取締役を招聘することは、建設業許可取得のための有効な戦略となります。経験豊富な取締役は、建設業に関する専門的な知識や経験を持っており、建設業許可取得のための要件を満たす上で大きな力となります。また、経験豊富な取締役は、建設業に関する戦略の策定や、現場での技術指導などを担当し、企業の成長に貢献することができます。そのため、建設業への参入を検討している企業は、経験豊富な取締役の招聘を検討する価値があります。
許可取得後の注意点と更新手続き

許可の更新手続き
建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というわけではありません。建設業許可には有効期間があり、5年ごとに更新が必要です。この更新手続きを怠ると、許可が失効し、再び許可を取得する必要が生じます。許可が失効した場合、再び建設業を営むためには、最初から許可申請を行う必要があり、時間と手間がかかります。更新期限をしっかりと管理し、必要な手続きを忘れずに行いましょう。
更新手続きは、有効期間満了日の3ヶ月前から受け付けています。更新手続きを行う際には、更新申請書、経営状況分析結果、納税証明書などの書類を提出する必要があります。これらの書類は、事前に準備しておくことをおすすめします。また、更新手続きには、手数料がかかります。手数料の金額は、許可の種類や申請内容によって異なります。
更新手続きは、都道府県知事許可の場合は各都道府県庁、国土交通大臣許可の場合は地方整備局で行います。 更新手続きを行う際には、事前に各都道府県庁や地方整備局のホームページで、手続きの詳細を確認しておくことをおすすめします。また、更新手続きに不安がある場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。行政書士は、建設業許可に関する専門家であり、更新手続きの代行や、必要な書類の作成などをサポートしてくれます。更新期限を過ぎてしまうと、許可が失効してしまうため、早めの手続きを心がけましょう。
変更届の提出
建設業許可を取得した後、会社名、所在地、役員などの情報に変更があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。
この変更届は、建設業法で定められた義務であり、怠ると行政指導の対象となることがあります。変更届の提出期限は、変更があった日から30日以内と定められています。 変更届を提出する際には、変更届出書、変更事項を証明する書類(登記簿謄本、住民票など)を提出する必要があります。
これらの書類は、事前に準備しておくことをおすすめします。また、変更届の提出には、手数料はかかりません。変更届は、都道府県知事許可の場合は各都道府県庁、国土交通大臣許可の場合は地方整備局で行います。 変更届を提出する際には、事前に各都道府県庁や地方整備局のホームページで、手続きの詳細を確認しておくことをおすすめします。変更届の提出を怠ると、建設業法違反となり、行政指導の対象となることがあります。行政指導には、指示処分、営業停止処分などがあり、最悪の場合、許可を取り消されることもあります。そのため、変更があった場合は、速やかに変更届を提出するようにしましょう。また、変更届の提出だけでなく、建設業許可通知書の記載事項も変更する必要があります。建設業許可通知書の記載事項を変更するためには、書換え交付申請を行う必要があります。書換え交付申請を行う際には、建設業許可通知書、変更事項を証明する書類(登記簿謄本、住民票など)を提出する必要があります。書換え交付申請にも、手数料がかかります。
定期的な経営状況の報告
建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、経営状況に関する報告書を提出する必要があります。この報告書は、建設業者の経営状況を把握し、建設業の健全な発展を図ることを目的としています。
報告書には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書などの財務諸表が含まれます。 これらの財務諸表は、適切な会計処理を行い、正確に作成する必要があります。また、報告書には、建設工事の施工状況、従業員の状況、安全衛生管理の状況なども記載する必要があります。報告書は、都道府県知事許可の場合は各都道府県庁、国土交通大臣許可の場合は地方整備局に提出します。報告書の提出を怠ると、建設業法違反となり、行政指導の対象となることがあります。 行政指導には、指示処分、営業停止処分などがあり、最悪の場合、許可を取り消されることもあります。そのため、報告書は、必ず期限内に提出するようにしましょう。報告書の作成には、専門的な知識が必要となるため、会計事務所や税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。専門家は、適切な会計処理を行い、正確な報告書を作成してくれます。また、報告書の作成だけでなく、経営状況の分析や改善策の提案なども行ってくれます。定期的な経営状況の報告は、建設業者の義務であるとともに、経営改善の機会でもあります。報告書を通じて、自社の経営状況を把握し、問題点を改善することで、より健全な経営を行うことができます。
まとめ:建設業許可取得は専門家への相談も検討を
建設業許可の取得は、要件が複雑で時間もかかる場合があります。特に、実務経験の証明や、専任技術者の要件を満たすことなどは、専門的な知識が必要となるため、個人で行うにはハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。
そのような場合は、専門家である行政書士に相談することで、スムーズな許可取得が可能になります。
行政書士は、建設業許可に関する専門家であり、申請書類の作成、実務経験の証明、専任技術者の要件確認など、許可取得に関する様々なサポートを提供してくれます。 行政書士に依頼することで、時間や手間を大幅に削減することができます。
また、専門的な知識や経験に基づいたアドバイスを受けることができるため、許可取得の可能性を高めることができます。
当事務所YAS行政書士事務所は、建設業許可を専門に取り扱っており、建設業に関する豊富な知識と経験を持っており、多くの建設業者をサポートしてきた実績があります。当事務所に相談することで、自社の状況に合わせた最適なアドバイスを受けることができます。建設業許可の取得は、建設業者にとって非常に重要なことです。許可を取得することで、より多くの工事を請け負うことができるようになり、事業の拡大につながります。また、許可を取得していることは、顧客からの信頼を得ることにもつながります。建設業許可の取得を検討している方は、ぜひ専門家への相談を検討してみてください。