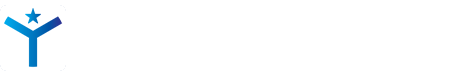建設工事を仕事として行う場合、個人事業主でも建設業許可が必要な場合が多々あります。建設業許可を取得するにあたり知っておくべきことを簡単にまとめます。

建設業許可の重要性
建設業許可は、建設工事を行う上で必要となる場合があります。一人親方でも、許可の取得が必要なケースが増えています。2022年のデータでは、許可取得業者の約20%が個人事業主です。
個人事業主と法人の違い
簡単なところだと、個人事業主は個人に許可が与えられ、事業主の死亡で許可は消滅します。法人は法人に許可が与えられ、代表者の死亡後も許可は続くということが一番の違いになります。
また、個人事業主が法人化する場合、新たに許可を取得する必要があります。ですので、のちに法人予定がある場合、建設業許可取得時に一緒に取得することをおすすめいたします。
建設業許可のメリットとデメリットをおさらい
メリット: 取引先への信用増加、取引範囲の拡大。
デメリット: 許可取得には多くの要件があり、書類の準備が大変。
許可取得要件のおさらい
経営業務の管理責任者の配置: 一定の経験が必要。
専任技術者の配置: 専門的な知識や経験が求められる。
誠実性の証明: 違法な請負契約がないこと。
財産的基礎: 一定の資金力が必要。
欠格要件の非該当: 犯罪歴や過去の許可取り消し等がないこと。
【深堀り解説】「建設業許可 個人事業主が取得」時の最重要ポイント
個人事業主が建設業許可を取得する際、最も高いハードルとなるのは、「経営業務の管理責任者(経管)」の要件をクリアするための実務経験の証明です。
経営経験の証明方法の難しさ
個人事業主本人が経管を兼任する場合、過去5年または6年分の建設業経営経験を証明する必要があります。ここで、単なる確定申告書の控えだけでは「経営の実態」を証明する書類として不十分な行政庁がほとんどです。
行政庁が求めるのは、その経営期間中に実際に建設工事を請け負っていたことを証明する客観的な証拠です。具体的には、以下の資料を経営期間全体(5年または6年)にわたり、欠けなく揃える必要があります。
- 工事請負契約書、注文書、請求書の控え
- 上記書類に対応する通帳の入金記録や領収書
これらの第三者による証拠が一つでも抜けていると、申請は受理されません。個人事業主が建設業許可を取得するためには、まずこの膨大な資料収集と整理から始めることが、成功への第一歩であり、難易度を分ける最大の要因となります。
必要書類のおさらい
一般書類: 建設業許可申請書、営業所一覧表など。
経営業務の管理責任者: 確定申告書の写し、経験を証明する工事請負契約書や注文書など。
専任技術者: 学歴や実務経験を証明する書類、国家資格の合格証明書など。
許可が不要な工事のおさらい
軽微な建設工事、例えば建築一式工事で1500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、建築一式工事以外で500万円未満の工事では許可は不要。
許可取得の費用面
建設業許可取得には費用が発生します。申請料、書類作成、場合によっては専門家への相談料などが含まれます。
費用は地域や必要な書類の量、手続きの複雑さによって異なります。
許可取得後の義務
許可を取得した後は、定期的な更新や変更がある場合の届出が必要です。
許可取得者は法律の変更や安全基準の更新に常に注意を払い、遵守する必要があります。
一人親方の特殊性
一人親方の場合、事業の規模が小さいため、許可取得のハードルが高く感じることがあります。
しかし、許可を取得することでより大きなプロジェクトへの参入機会が増えるなど、事業拡大のチャンスにつながります。
許可取得の時間枠
許可申請から許可取得までの時間は、申請の正確性や行政の処理速度によって異なります。
通常、申請から許可取得まで数週間から数ヶ月かかることが一般的です。
リスク管理
許可取得にはビジネスの信頼性向上が期待できる一方で、法令違反などにより許可が取り消されるリスクも伴います。
法律の遵守、適切な業務運営が必要です。
建設業許可の更新
建設業許可は一定期間ごとに更新が必要です。
更新時には財務状況や過去の業務履歴などの再確認が行われます。
建設業許可を個人事業主が取得する時に知っておくべきことまとめ

建設業許可は個人事業主にとっても重要ですが、取得は複雑で時間を要するプロセスです。
許可取得のためには、経営管理責任者や専任技術者などの要件を満たし、費用の準備、時間的な計画、リスク管理などを慎重に考慮し、準備することが重要です。
許可取得は事業の発展に大きく寄与しますが、その後の義務やリスクにも注意を払う必要があります。