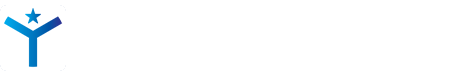建設業許可を取得できる確率は、当事務所にご依頼いただければ帆の取得は可能です。
ただし、必要な要件や書類の提出はありますので、作業量は意外とあります。
ですので、ご自身で取得することも可能ですが、その時間を考えたら、建設業許可専門の行政書士にご依頼いただくのが手っ取り早いと思います。

建設業許可の必要性
建設工事を営業として行う場合、特定の状況下で建設業許可が必要になります。特に、元請業者から許可の取得を求められることが増えており、融資を受ける際にも許可の取得が条件になることがあります。軽微な工事(1件あたりの請負金額が500万円未満)を行う個人事業主でも、許可が求められる傾向にあります。
許可取得の要件
建設業許可を得るためには以下の5つの要件が必要です。
1、経営管理責任体制の整備: 役員に一定以上の経験が必要。
2、専任技術者の配置: 営業所ごとに一定の資格・経験を持った人を配置。
3、財産的基礎の確立: 一般建設業と特定建設業で異なる要件。
4、誠実な契約実績: 違法な請負契約がないこと。
5、欠格事由の不存在: 犯罪歴や暴力団との取引がないこと。
経営管理責任体制の要件
この要件は、常勤役員が建設業に関する5年以上の経営業務の管理責任者としての経験、または管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する必要があります。この要件を満たすには、適切な経験を書面で証明することが重要です。
専任技術者の要件
専任技術者は、特定建設業許可と一般建設業許可で異なる資格要件があります。特定建設業では一級国家資格者や特定の実務経験者が必要で、一般建設業では二級国家資格者や実務経験者が求められます。
財産的基礎の要件
一般建設業では自己資本500万円以上、または資金調達能力が求められます。特定建設業では資本金2000万円以上、自己資本4000万円以上、欠損額が資本金の20%以下、流動比率75%以上が必要です。
取得確率はどのくらい?
建設業許可申請ができる確率は、個人事業主にとっては約5%〜10%程度とされています。許可申請に必要な書類のハードルが高く、経営経験の証明や適切な書類の準備が難しいためです。
ただし、建設業専門の行政書士にご依頼いただければ、必要書類などを的確に指示いたしますので、取得率が一気に上がります。
必要書類の準備
経験期間の証明: 確定申告書の控え原本や電子申告の証明。
経験内容の証明: 建設工事の請負契約書、注文書、請求書、入金記録など。
許可取得後の本当の難易度:維持と更新のチェックポイント
建設業許可の「難易度」は、単に取得申請をパスするだけで終わりではありません。許可取得後の維持・管理(コンプライアンス)も、事業の継続性において非常に重要です。行政庁は、申請時だけでなく、毎年の事業年度終了報告(決算報告)を通じて、事業者が引き続き許可要件を満たしているかを継続的に厳しくチェックしています。
特に、多くの事業者がつまずき、更新や許可の継続を危うくする重要な義務は以下の2点です。
- 社会保険の加入: 許可業者には、法人・個人を問わず、要件を満たす従業員を健康保険・厚生年金に加入させる義務があります。未加入の状態で更新時期を迎えると、「適正な施工体制」を満たさないと判断され、許可の更新が不許可となる最大の要因の一つです。
- 変更届の徹底: 経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の退職、営業所の移転、資本金の変更など、重要事項に変更があった場合、30日以内に「変更届」を提出する義務があります。これを怠ると、将来的に許可の取消しや更新の不許可につながる可能性があります。
これらのコンプライアンス体制を整え、許可を「生き続ける」事業者にこそ、大規模工事のチャンスが継続的に訪れます。
建設業許可の取得確率ってどのくらい?まとめ

建設業許可の取得は、個人事業主にとって複雑で難易度が高いプロセスです。特に、経験と財産的基礎を証明する書類の準備が大きな障害となることがあります。そのため、許可申請が成功する確率は比較的低く、計画的な準備と対策が必要です。
取得時に、同時に法人化される方も結構多くいらっしゃいます。法人化と同時のご依頼は格安で可能です。お問い合わせくださいませ。