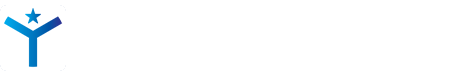建設業の許可を個人事業主(一人親方を含む)として取得する際のポイント、メリット・デメリット、必要書類等についてまとめます。
個人事業主であっても一定の取得要件を満たすことが証明できれば、建設業許可の取得は可能です。
取得には法人と同じような要件が求められますのでメリットデメリットを含め検討しましょう!

許可が不要なケースとは
建設業の許可が不要なのは「軽微な建設工事」のみです。具体的には、以下になります。
・建築一式工事: 工事1件の請負代金が1500万円未満、または150㎡未満の木造住宅工事。
・建築一式工事以外: 工事1件の請負代金が500万円未満。
個人事業主の許可取得要件とは
- 人的要件
経営管理責任体制の整備: 適正な経営能力と社会保険への加入が必要。
専任技術者: 一定の資格や実務経験が必要。
- 財産的要件
一般建設業許可: 自己資本が500万円以上。
特定建設業許可: 資本金2000万円以上、自己資本4000万円以上などの条件。
- 営業所の要件
独立した営業所が必要。自宅のみでは不可。
- 欠格事由の要件
違法行為や自己破産などの欠格事由がないこと。
【重要】個人事業主特有の要件クリア戦略と法人化の検討
個人事業主が建設業許可を申請する際、特に重要かつ困難なのが「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」の証明です。個人事業主は、事業主本人がこの両方を兼任できますが、証明書類の準備には特に注意が必要です。
経管の証明では、単に確定申告書を提出するだけでなく、過去5年以上にわたり建設業を営んできた実態を示すため、契約書、注文書、請求書などの客観的な証拠書類を綿密に揃える必要があります。この実態証明こそが、個人事業主の許可申請における最大の関門となります。
許可取得後の展望として、事業規模の拡大や節税対策を検討する時期が来たら、法人化(会社設立)のタイミングを計画的に見極めるべきです。法人化は、公共工事への参入や大規模な元請け工事の受注、そして社会保険への対応といった面で、個人事業主としての許可よりも格段に信用力が高まります。許可取得はあくまでスタートライン。次のステップとしての法人成りを視野に入れ、事業の成長を最大化しましょう。
建設業の個人事業主と一人親方とは
個人事業主とは責任者として事業を営み、スタッフを雇用するケースもある。
一人親方:とは家族や身内だけで事業を営む人。
必要書類
経営業務の管理責任者: 5年以上の経験を証明する書類(確定申告書の写し、工事請負契約書など)。
専任技術者: 学歴や実務経験、資格を証明する書類。
メリット
信用力の向上: 個人事業主で建設業許可を取得することは比較的少数であるため、差別化が図れる。
大規模建設工事の受注: 軽微な建設工事を超える工事の受注が可能。
低コストでの事業維持: 法人税の均等割がかからない、社会保険への任意加入など。
デメリット
費用の発生: 許可取得や更新には費用がかかる。
受注の不確実性: 規模の大きな工事の受注が確実ではない。
決算報告書の提出義務: 許可取得後は決算報告書の提出が必要。
個人事業主が建設業許可を取得する時に必要なことのまとめ
個人事業主が建設業許可を取得することは可能ですが、要件を満たすための書類の準備や費用の発生など、検討すべき点が多いです。一方で、信用力の向上や事業の拡大といったメリットもあります。メリットとデメリットを総合的に考慮し、許可取得の判断をすることが重要です。