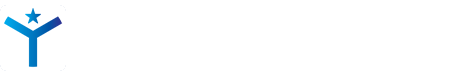建設業の許可を取得しようとする業者は、29業種の中から自社のメインとする工事などを考慮して必要な業種を選択することになります。
今回は5つの業種を紹介します。(記事を5回に分けて29業種を紹介します)

建設業許可における主要5業種の解説
建設業許可では、29種類に分類される専門工事業の中から、実際に行う工事に応じた業種を選び、許可を取得する必要があります。ここではその中でも代表的な5業種、特に総合的な工事から木工、左官に関わる業種を中心に解説します。
① 土木工事業(一般土木工事)
定義:
総合的な企画・指導・調整のもと、道路・橋梁・ダム・上下水道・河川護岸・土地造成などの土木構造物を新たに建設する工事、または補修・改造・解体する工事。
特徴:
公共インフラに関わる工事が中心となるため、工事規模も大きく、発注者の大半が国や地方自治体などの官公庁です。
対象となる工事の例:
- 道路・舗装工事
- 河川・堤防の護岸工事
- 橋梁工事
- 上下水道の敷設・修繕
- ダムやトンネルの施工・補修
- 宅地造成など土地整備
ポイント:
土木工事業は、複数の専門工種を統合して管理する能力が求められるため、現場の調整力・法令遵守・安全管理体制が問われます。また、建設コンサルタントや測量士との連携も必要です。
② 建築一式工事
定義:
総合的な企画・指導・調整のもと、住宅やビル、商業施設など建築物全体を建設する工事。その内容が多岐にわたるため、複数の専門工事を統括する性質を持ちます。
特徴:
建築主(施主)と直接契約を結び、建物の設計・施工から引き渡しまでを管理。ゼネコンや工務店が該当することが多く、発注者との契約額が大きくなりやすい業種です。
対象となる工事の例:
- 戸建住宅の新築
- マンション・ビルの建築
- 学校・病院・工場の建設
- 既存建築物の増改築
ポイント:
工事の「一式請負」に当たるため、発注額が1,500万円以上または延床面積150㎡超の木造住宅を施工するには建築一式工事の許可が必要です。建築士・現場管理者の配置要件なども厳しく、一定の体制が必要となります。
③ 大工工事業
定義:
木材の加工や取り付けにより、建物の骨組みや内装などを施工する工事。木製設備(棚、天井、建具など)の設置も含まれます。
特徴:
住宅の新築・リフォーム現場での作業が中心で、手作業による丁寧な施工技術が求められます。近年はプレカット材の導入などによって、工法も進化しています。
対象となる工事の例:
- 木造住宅の構造躯体の組立
- 和室の造作・建具の設置
- 天井板やフローリングの施工
- 木材の下地組み
ポイント:
個人事業主の方や職人出身の事業者が多く登録している業種です。500万円以上の木工工事を元請けとして行う場合には許可が必要。住宅リフォームや増改築の場面で活躍する業者にとって重要な業種です。
④ 左官工事業
定義:
壁土、漆喰(しっくい)、モルタル、プラスター、繊維素材などを使い、壁・床・天井などに塗装・塗りつけ・吹付けを行う工事です。
特徴:
日本伝統の仕上げ工法から、モルタルや珪藻土を使った現代建築の内外装まで幅広く対応。仕上げ技術の精度・美観に直結するため、職人の技術が工事品質に大きく影響します。
対象となる工事の例:
- 外壁モルタル仕上げ
- 室内しっくい・珪藻土の塗り壁
- 玄関や土間のコンクリート仕上げ
- 床のモルタル均し工事
ポイント:
施工者の技能が完成度に直結する業種のため、熟練職人の育成や技能者の確保が重要です。500万円以上の左官仕上げ工事を請け負う場合には許可が必須となります。
⑤ 自社の業種が含まれていましたか?
このように、建設業許可は単なる「業界ライセンス」ではなく、それぞれの施工業種に応じた専門性と責任を明確にする制度です。自社の主力工事がどの業種に該当するかを明確にし、必要な許可の取得を行うことで、営業活動の幅が広がり、元請業者や顧客からの信頼も得られます。
次回は「その他の5つの業種」について解説予定です。塗装・とび土工・内装など、特にリフォーム業界で多い業種についても詳しく触れていきます。
建設業許可のご相談は、YAS行政書士事務所までお気軽にどうぞ。取得実績多数・ご相談無料です。