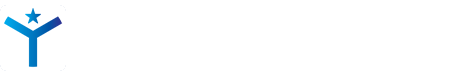建設業許可に関する大臣許可と知事許可の違い、営業所の要件、そして県外での工事の可能性について解説します。
建設業許可は仕事をする各都道府県ごとに免許を取らないといけないのか?という疑問を解決いたします。

建設業免許における大臣許可と知事許可の違い
建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」の二種類がありますが、違いは営業所の所在地に基づいています。
大臣許可は二つ以上の都道府県に営業所を持って営業する場合に必要です。
知事許可は一つの都道府県内にのみ営業所を持っている場合に取得します。
例えば、東京都に本社があり、愛知県に支店がある建設会社は大臣許可が必要ですが、東京都内に複数の営業所を持つが他県にはない場合は知事許可で十分です。
大臣許可・知事許可を選ぶ前に確認すべき「営業所の実体」
建設業許可における大臣許可と知事許可の選択基準は、「複数の都道府県に契約機能を持つ営業所があるかどうか」に尽きます。ここで最も重要なのは、単に支店登記や連絡先があるだけでは不十分だという点です。行政庁が認める「営業所の実体」とは、以下の要件をすべて満たす場所を指します。
- 契約機能の保有: 見積もり、入札、契約締結といった建設工事の請負契約に関する業務を実質的に行っていること。
- 物理的な独立性: 居住空間や他事業のスペースと明確に区分され、建設業専用の事務所として使用されていること。
- 常勤者の配置: その営業所に、経営業務の管理責任者(または建設業法施行令第3条の使用人)と、申請業種に対応する専任技術者が常勤していること。
例えば、「東京に本社(知事許可)があり、大阪の建設現場に事務所を設けた」というケースでは、大阪の事務所が単なる現場事務所(置き場や連絡所)であれば、大臣許可への切り替えは不要です。しかし、大阪で請負契約を締結する業務を始めた途端、その事務所は「営業所」と見なされ、大臣許可への切り替えが必要となります。この「契約締結機能の有無」こそが、知事許可と大臣許可を分ける最大の分水嶺です。
営業所の要件とは
建設業法上での営業所とは、以下の要件を満たす事務所です。
1、請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること。
2、電話、机、各種事務台帳等があり、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること。
3、契約に関する権限を持つ者(「経営業務の管理責任者」または「建設業法施行令第3条に規定する使用人」)が常勤していること。
4、専任技術者が常勤していること。
5、常時使用する権原を有していること。
連絡所や置き場など、契約機能を持たない事務所は営業所に含まれません。また、建設業以外の事業のみを行う事務所も営業所とは見なされません。
県外での工事の可能性
知事許可を取得した場合でも、許可を取得した都道府県以外の場所で工事を行うことは可能です。しかし、県外の営業所では500万円以上の工事の請負契約を締結することはできません。そのため、県外で請負契約を締結する場合は、その事務所が営業所としての条件を満たし、建設業許可を取得する必要があります。この新たな営業所が県外にある場合は大臣許可が必要になります。
建設業許可は許可以外の件で仕事は受けられないのか?のまとめ
建設業許可の取得においては、大臣許可と知事許可の区別が重要です。営業所の定義や設置場所に応じて適切な許可を取得する必要があります。知事許可を持っていても、他県での工事は可能ですが、営業所としての機能を持たない場所では請負契約の締結はできません。適切な許可の取得はビジネスチャンスの拡大につながり、事業の安定と拡大に寄与します。